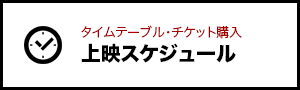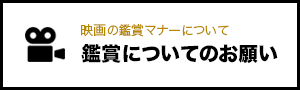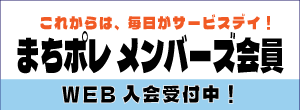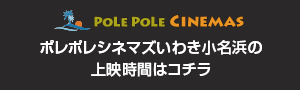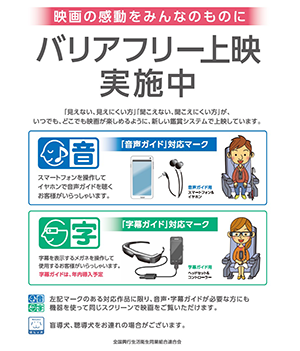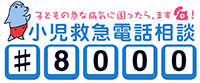◆ほぼ毎号、イントロが浮かぶと書き出すというスタイルですが、最新169号は「回覧ノート」というキーワードだけで始めたら、結果的に追悼特集のような内容になってしまいました。
本文中の大船撮影所見学や小原玲君のくだりは、電子版の64号(通巻54号)で触れているのですが、言ってみればそれも追悼特集のような内容でした。
今回は、その「前号は」という書き出しで始めた4年前の55号を紹介します。50代未満だと、知らない(あるいは、聞いたことがあるという程度の)映画しか登場しないかもしれませんね。
◆『まちポレ壁新聞』最新169号『記憶の彼方』(9/28発行)は、5階ロビーに掲示中です。
※141号以降のバックナンバーのファイルもあります。
まちポレ壁新聞 №55 2021年9月25日
脇役グラフィティ
Time My-Scene ~時には昔の話を~ (vol.20)
結果的に前号は、追悼特集のような内容になっていました。
古尾谷雅人さん、斎藤洋介さん、蟹江敬三さん、そして、渥美清さんをはじめとするとらやの面々の多くがすでに亡くなっています。
「車輪の一歩」で共演した…と一度書きかけて勘違いだったことに気付きましたが、阿藤快さん(私には阿藤海という字の方がしっくりきます)もこのドラマに出ていたような気がしてました。加えて、亡くなっていたことも失念していたのです。いつでもパワー全開で唾を飛ばしながら喋りまくり、ガツガツと食べて、殺しても死なない奴、勝手にそんなイメージを抱いていたのに。好きな、画面にいつも写っててほしい脇役がみんな逝ってしまった、そんな感じです。
阿藤さんが絡んだのは「ヒポクラテスたち」(1981年)の方でしたね。
この映画、もう一度見たいなぁ。大森一樹監督の<軽さ>がいい方に出た快作です。いや、軽さというと誉め言葉にならないかもしれないから〈軽快さ〉と言った方が適切かな。ベストワンになるような作品ではないけれど、でもベストワンに選んでくれたらありがとうと言いたい、そう思わせる映画です。
共演の役者もいいものなぁ。
斎藤洋介さんと内藤剛志さんはこれが映画デビュー作、古尾谷さんはにっかつロマンポルノから一般映画への転身、伊藤蘭ちゃんは〈普通の女の子〉からの復帰作と、出演者の多くが〈きっかけ〉になった作品と言えます。他にも柄本明さんや真喜志きさ子さん、更に監督が敬愛する鈴木清順監督や手塚治虫さんの友情出演?まであり、もちろん原田芳雄さんが出てるのは言うに及ばずです。
シナリオが掲載されたパンフレットはあるんです。
ATGが公開した作品のパンフレットは「アートシアター」というタイトルで刊行されていました。私が所持しているのは129号の「北村透谷・わが冬の歌」から146号「遠雷」まで、虫食いでの6冊。「ヒポクラテスたち」は間の142号に位置しています。ちょうど二十歳前後の多感だったころで、映画も貪るように見てました。タイトルロールを演じたみなみらんぼうさんは知ってても、北村透谷という詩人は初めて聞いたし、今にして思えばなんで見て、しかもパンフレットまで、どして? 監督山口清一郎、主演田中真理という名前に魅かれたのかな? 歌舞伎町にあった地球座という映画館で、「変奏曲」というやはりATG作品と、プラスもう一本と三本立てだったような記憶はあるけど、思い出せない…。
残りの三冊は、公開順に「Keiko」「海潮音」「ガキ帝国」。
晩年のATGの方がアート一辺倒の初期とは違い、バラエティに富んで私には身近に感じたし、魅力的でもありました。
いつもの長いあとがき
ブロックブッキング制だった当時、ATGは東宝傘下ということもあり、ローカルでは東宝封切館において、興行的に弱そうな作品のテコ入れで陽の目を見ることが多かったですね。※以下はいずれも水戸の東宝封切館でのことです。
「Keiko」は、「戒厳令の夜」という五木寛之原作というだけが売りの作品の補填でした。もう細部は忘れているけれど、カナダ人のクロード・ガニオン監督がドキュメンタリータッチで普通のОLの日常を描き、新鮮でした。白地に真っ赤な「Keiko」というタイトルがデカデカと斜に書かれたポスターが、『23才 ヴァージンなんておかしいですか』という惹句とともに忘れがたい。
一方、大作一本立てでメインだったはずの「戒厳令の夜」で浮かんでくるのは、樋口可南子さんがちょっと斜に構えて正面を向いたポスターだけ。
五木寛之原作では「燃える秋」という三越が製作した映画があり、私はずっと「もう頬づえはつかない」が併映されたと思い込んでいましたが、全くの勘違い。新春第二弾の1月に、<百和>の「炎の舞」のロングと二本立てでした。
タイトルから勝手に秋の公開で、ポスターも、真っ赤に色づいた紅葉をバックに主演の真野響子さんが正面を向いた構図だったと思っていたのですが、どこを調べてもそんなの出てこず。宮本輝さんの「錦繍」という本があり、「戒厳令の夜」とそれらをミックスして勝手に空想を膨らませていただけでした。
鮮明に覚えているのは、作詞=五木寛之、作曲=武満徹によるハイファイセットの主題歌だけ。三越はお金の使い方を間違ったのか。ま、主題歌は隠れた名曲として残っているから、広告費と考えれば安かった?
「サード」に至っては、調べ直してビックリ! 1978年リバイバルの「風林火山」と二本立てでした。水と油、相乗効果というよりは全くの別物。<実質>入替制みたいなものですかね。
ちょっと余談になりますが、昔の東宝は、結構リバイバルをしてくれましたね。「天国と地獄」は確か1977年に格安料金で公開したんじゃなかったかな?
岡本喜八監督の「ブルークリスマス」はカルトムービーと化してますが(つまり不入りだったということですね)、「曽根崎心中」を併映に選んでました。名画座の番組みたいですね。
前号で書いた「太陽を盗んだ男」は、橋浦方人監督のデビュー作「星空のマリオネット」が同時上映(次作が「海潮音」)。これに主演した三浦洋一さんも40代という若さで故人に。ドラマ「池中玄太80キロ」が一番認知されたかな。
このころは自分が一番映画館に入り浸っていたこともあるけれど、亜湖さん、竹田かほりさん、森下愛子さんなど、旬を迎える女優さんの登場とも重なります。最後の二人は日本を代表するシンガーソングライターの奥様か。 (沼田)