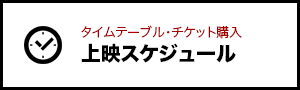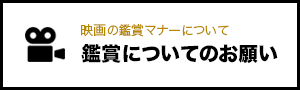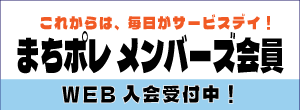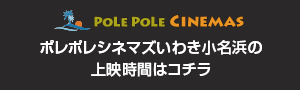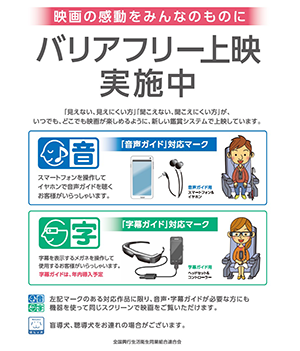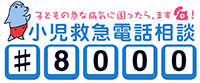◆最新156号は、BSで放送された番組についてしたためたのですが、2年半前にも、BSが映画アーカイブの裏側を取材した番組について書いていました。しかし、いまだに注意しないと、積年の習慣でついついフィルムセンターと口走りそうになります。
それにしても、国がコレクションしたものは歴史的資料で、私が捨てないで残しているものはただのゴミ、捨てるよーと家族からは脅かされるという、この差はいったい何なの(笑)。
◆『まちポレ壁新聞』最新156号『アンテナ立てて』(4/27発行)は、5階ロビーに掲示中です。
※121号以降のバックナンバーのファイルもあります。
まちポレ壁新聞 №88 2022年9月27日
「見る」ことと「残す」こと
Time My-Scene ~時には昔の話を~ (vol.53)
冒頭から身も蓋もないことを言ってしまうと、映画を「見る」という基本的な行為において、私はあまり熱心なファンとは言えないかもしれません。たまにしか入らない小名浜勤務の時にまちポレの常連さんにお会いすると、心底感心してしまいます。
テレビ放映にしても、まとめてたまにBSプレミアムをチェックする程度なので、見逃すこともしばしばです。劇場用映画の場合は番組欄が色付けしてあるので見やすいのですが、それ以外だとチェックまで追いつかないのが実情です。
そんな私に友人が、「ザ・バックヤード 知の迷宮の裏側探訪」という番組を教えてくれました。実は当人も見逃してしまい、数日後に再放送があるということを知らせてくれたのです。9月20日に再放送されたのは、国立映画アーカイブの裏側の世界。それは、いくつもの驚きの連続でした。
まず、フィルムを水平にセットし、デジタル化するためのチェックをしているのが目からウロコ! フィルムを缶から出し入れするときは、必ず縦(床に対して垂直)にするように上の人から教わりましたから。
扱ったことのない方に状況を説明するのは難しいのですが、フィルムの巻き芯付近がスポッと抜けてしまった場合のどうしようもない焦燥感。次の上映、あるいは返却までに原状回復しなければなりません。焦り、泣きたくなります。逃げ場はないのにその場から逃げ出したくなるほどです。
映画アーカイブが紙の収集保存にも力点を置いているのは以前も記しましたが、その修復方法は驚愕でした。あくまでも〈仮〉の処置なのです。それは、将来別の良い修復方法が見つかった場合に備えてのためで、絵画など美術品と同様の方法ということでした。
ポスターだけでなく、カレンダーまで保存しているのにはニンマリ。私も残してますから(笑)。
加えて、映画関係者の私物も残していて、番組では志村喬さんの番傘を紹介していました。唐傘は実家にもあるけれど、ウチのは浅草花やしきのお化け屋敷ぐらいでしか使い道がない(笑)。
更にカメラは、相模原にある保存のための別館にも初侵入。
その冒頭、通路の屋根にある長方形の天窓のサイズがバラバラなのが分かりますか?というジャブを出してきました。これは、映画関係者ならすぐ分かりますね。こういう遊び心は嬉しくなります(注/寸法がスクリーンサイズ比)。
驚いたのは、重要文化財に指定されているフィルムに対する保存の姿勢です(重文のフィルムがあるのも初めて知りました)。それこそ厳重管理され、可燃性フィルムは燃えてしまうと水で消えないにも関わらず、スプリンクラーが設置されています。その理由を聞いて驚き、また感心しました。水冷して延焼を防ぐためだそうです。また、外壁はコンクリート壁で二重に囲んでいます。これも万が一の爆発被害に備えてということです。
このように全てに於いて〈念には念を〉の姿勢が貫かれているのです。
コロナ禍の外出自粛に際して、映画は不要不急という議員さんの発言にはがっかりさせられましたが、国の『本気の姿勢』には安心感嘆しました。
いつもの長いあとがき
休日に時間が空いたので、録りためていた未見リストから「わが谷は緑なりき」を見ました。初見です。アカデミー賞を多数受賞した名作で、ジョン・フォード監督作品ということ以外、内容に関する予備知識はゼロに近い状態でした。
フォード監督だから当然、西部劇だと思ってました。そしたら何と、炭鉱で働く家族と少年の成長物語だったので驚きました。開始早々、いきなりズリ山が出てくるのです。〈おらが町〉の物語じゃないのーっ。1941年の製作ですから、80年も経っているにも関わらず、全く色褪せないヒューマニズム溢れる傑作で、黒澤明監督の「赤ひげ」に思いを馳せました。
ところでこの作品は、『アメリカ国立フィルム登録簿』に登録された作品です。以前からこの名称はたびたび目にしていましたが、今回いろいろ調べてみました。ひと言で言うと、日本の映画アーカイブの仕事に近いのですが、作品の選定が政府、管理は各映画会社となっているのが日本と違うところです。また、〈いわゆる名作〉一辺倒ではなく、「我々がどのような人々か、どのような国民なのかをよく示す作品」が選定基準とのことで、ニュース映画、実験映画、アマチュアのホームビデオまでが対象となっているのが斬新で、興味深いところです。
これを見た日は、日中は小名浜に出向き「サバカン」を見ていました。
こちらも、「スタンド・バイ・ミー」風という予備知識しかなかったのですが、いや、そのひと言で全てを言い当てているとも言えます。やはり家族愛と少年の成長物語で、全くの偶然とはいえ、80年以上も隔てて日米の同じようなテーマを扱った作品を同日に見た不思議さは、<呼ばれた>のかなぁと思ってしまったほどです。
しかし。
予想されたこととはいえ、見事なまでの不入りです。このような作品がすんなりと受け入れられるほど、日本の土壌はまだ成熟していないということの証左ですね。 (沼田)