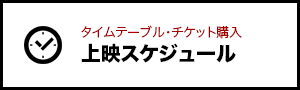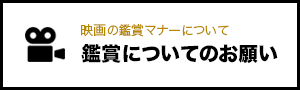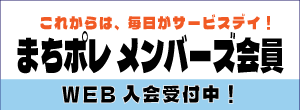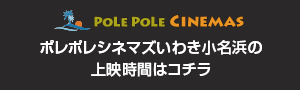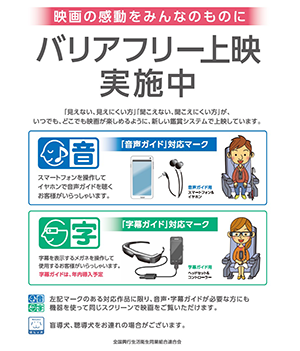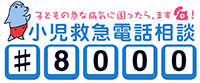◆今回は、まるまる5年前の18号をご紹介します。再掲に至った理由は、最後まで読んでいただくと分かるかと。4/11から上映する「天国の日々」。1978年製作ですが、日本公開はその5年後。今回42年ぶりとなるリバイバルです。私自身いわきに住んでいなかったし、記録もないので不明ですが、いわき地区初公開の可能性もあります。
4階ロビーに、その封切時のパンフレットと新聞記事を展示しています。パンフには『Cinema square Magazine №13』と記されており、要するにシネマスクエアとうきゅう13番目の上映作品ということですね。
実は、18号本文中にある「キャリー」も、テレンス・マリック監督と間接的に接点があるんですがね。※好きな映画の前説は長くなる…。
◆『まちポレ壁新聞』最新153号『サヨウナラと敬礼』(4/1発行)は、5階ロビーに掲示中です。
※121号以降のバックナンバーのファイルもあります。
まちポレ壁新聞 №18 2020年4月7日
いつ、どこで
タイトル未定の新しいコラム (その18)
「スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス」の時だから、もう20年以上前になりますが、電話で問い合わせてくる方の多くが、「エピソード1」と言ってくるのに違和感を覚えました。私としては、メインタイトルの「スター・ウォーズ」と聞いてくるのが普通だと思っていたからです。あるいは、副題の「ファントム・メナス」か。少なくとも、最初の中間三部作の時はそうでした。この新シリーズの時に、20世紀フォックスがどういう売り方をしたのかは知らないのですが…。
そんなことを思い出したのは、今回の50作目の「男はつらいよ お帰り 寅さん」に接してです。
こちらは第49作の「特別編」から数えても「スター・ウォーズ」より前になりますが、むか~しと比べて、「寅さん」と言ってくる方が少なかった気がしました。大多数の方が「男はつらいよ」でした。もちろんそれだけの年月が流れ、また、作品の公開が毎年恒例ではなくなってますから、親近感が薄れたというのも理由に挙げられるでしょうね。
私の分析では、65歳が境目。それより上だと「寅さん」、60歳以下が「男はつらいよ」、その間に当たる世代が両方というデータが出ました。真偽は保証しませんよ(笑)。恒例でなく、高齢になったというのがオチですね。チャンチャン。
その「SW」シリーズと並び称される、もう一つの映画史に残る大ヒットシリーズの「バック・トゥ・ザ・フューチャー」。こちらも別の意味で、ずっと気になっています。
というのは、ポスター内に封切日がデザインされているからです。
私はこの作品あたりから、ポスター内に公開日が記されるのが一般化していったと記憶しています。きちんと調べてウラを取ったわけではありませんが。ただ全国一斉拡大公開が完全に定着し、メジャー作品が続編の公開日まで明記した特報まで製作して、次回作も「〇月〇日公開」と謳うようになったのはこのころです。
その沸点が「ジュラシック・パーク」だと言えます。
「〇月〇日、映画が変わる、スピルバーグが変える」とコピーにまでなってしまったわけですから。
同時に、この作品が公開された1993年という年は、日本で最初の外資系シネコンがオープンした年ですからね。
いつもの長いあとがき
何号か前に、「シネコンは構造が同じだから、どこで見たか記憶に残らない」といった旨のことを書きましたが、もう一つ大事なことを忘れていました。入替、全席指定定員制です。
要するに、立ち見なし。混んでるといっても必ず座れるんだから席取り合戦もないし、空いてても別の席へ移動もできないし。
私がキョーレツな記憶として残っているのは、まさに立錐の余地もなかったお正月の「ちびまる子ちゃん」。立ち見でも見られないほど混んでたにも関わらず、どうしてもという家族連れのお客様がいて、親御さんはただ入っただけ状態、お子さんはというとハイハイして立ち見の人込みをかき分け、通路前方に陣取って見てました。いやぁすさまじかった☺
あるいは、途中から入って好きな場面をもう一度見たりとか。当然ながらこれも出来ません。
東京の老舗名画座で、未見だった「ジョーズ」を見た時のこと。「キャリー」と二本立てだったのですが、封切で鑑賞済みの後者の途中から入り通路脇で立って見ていたら、例の手がガバっの場面で、脇に座って頬杖をついてみていたオジサンが、びっくらこいてずり落ちたのが印象的でした☺ こーゆー「余計な」楽しみも味わえないんだよなぁ。
もちろん、初見の作品を途中から入るという、そんな邪道なことはしませんよ。そーゆー見方が出来た達人は、殿山泰司さんか田中小実昌さんぐらいでしょうか⁉
そういえば、「ジョーズ」の封切時のメイン館は新宿ミラノ座でしたが、そのチェーン館で同じビル内にあったシネマスクエアとうきゅうは、ミニシアターの「はしり」でしたね。一脚七万円と言われたフランス製のソファーのようなシート、飲食は禁止、そして何より途中入場不可の自由席定員制。
オープニングの「ジェラシー」をはじめ、「ドレッサー」、柳町光男監督の「さらば愛しき大地」など、随分と楽しませてもらったし、開館第二か、第三弾だった「モスクワは涙を信じない」は自分たちのサークルで上映会までしたし。また、館名入りのパンフレットも小型でオシャレだったなぁ。
私は岩波ホールはついぞ入ったことがないけれど、高級感はあってもここは好きでしたね。今だったらそっくりそのまま、まちポレで上映しそうな作品ばかり。長いことお蔵だった幻の名作、リドリー・スコット監督の「デュエリスト 決闘者」もかけてくれたしね。ま、個人的にはいまだに「幻」のままなんですがね。チャンチャン←再登場☺
(沼田)