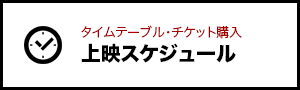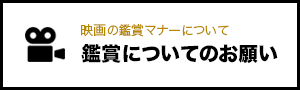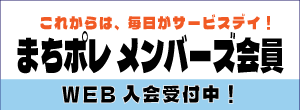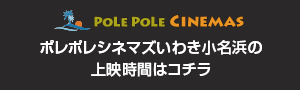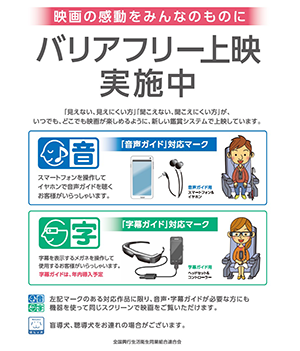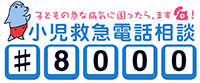◆電子版は、原則的に最新版の壁新聞の内容とシンクロ、またはインスパイアされたものの再録を基本としているのですが、今回は全く無関係のものです。
ファイルしてあるバックナンバーから、どこかのタイミングで掲載しようとマーキングしておいた3年前の71号を取りあげます。
◆『まちポレ壁新聞』最新161号『時を超えて』(7/1発行)は、5階ロビーに掲示中です。
※131号以降のバックナンバーのファイルもあります。
まちポレ壁新聞 №71 2022年4月11日
第一印象
Time My-Scene ~時には昔の話を~ (vol.36)
映画紹介にかかわらず、プロもアマも関係なく日常的に使っている言葉に「ネタバレ」というのがありますね。この言葉、いつごろから<大衆化>して、誰(雑誌やメディア)がきっかけで広がったのでしょうか?
批評をする上では、物語に触れなければ核心には迫れないわけで、それなのに何でもかんでも<ネタバレあり>だの、<ネタバレ含む> だのという文字が躍るようになりました。でも、映画批評を生業としているプロは別にして、趣味で映画を見ている以上は<選ぶ>という作業が必要になります。当然ながら、参考にするための指針が必要だから、何かしらは読んだりして<探り>を入れないとなりません。
昔はそんな注意表記はなかったですよ。書き手がどこまで配慮したかは別にして、私の場合だと「あ、ここまでだな。この先は核心に触れてそうだから読んでしまうと見る楽しみがなくなる」と中座して、あとは見てから読むようにしていました。おそらく誰でもそうですよね。
もう40年も昔になりますが、小林信彦氏は、「オチを書くな!」と<素人の売文>がはびこるようになったことを嘆いてました。
昨今のこの風潮はSNSの影響ですね、間違いなく。
そういう私自身素人なので、自分のことは棚に上げて書いてますけど。
忘れもしないのは「スター・ウォーズ 帝国の逆襲」の批評で、ダース・ベイダーにまつわる、物語の核に当たる部分をいきなり一行目でバラされたことです。再度書きますが、一行目ですよ。これでは防ぎようがない! 当人もそれぐらい驚いたからいきなり冒頭に持ってきたのでしょうが、これから見る人の初見の衝撃を<全ての>映画ファンから奪ったのですからね。犯罪ですよ、全く。以来、その「K」の評論は読まないことにしました。もちろんフルネーム覚えています。本当はゴシックで記したいぐらいです。
更に言うと、チェックしたであろう編集担当者もOKサインを出したわけです。これを掲載したのはキネマ旬報です。ああ……。私は二十歳前後だったけれど、抗議の投稿をしました。
ここ数年映画雑誌を読む機会が激減しているのですが、よくわからない肩書の執筆者が続出してますね。映画エッセイスト、映画コメンテーター、映画パーソナリティーなど。昔は、映画評論家(批評家)だけでしたけど。要するに、映画にまつわることを書いたり話したりしてお金をもらっています。ただ、評論家ではないので内容については責めないでねということなのかと、皮肉のひとつも言いたくなります。
いつもの長いあとがき
映画を選ぶ基準とまではいかないけれど、ポスターによってインスパイアされるというのはあります。
間もなく公開される「林檎とポラロイド」から浮かんできたのは、<静謐>という言葉。そこから、「ピロスマニ」という作品を思い出しました。バウシリーズの一本で1978年に公開されました。今回調べ直してみると、輸入されなかったのかお蔵入りだったのかは不明ですが、その9年も前の製作でした。また、2015年にはグルジア語オリジナル版が「放浪の画家ピロスマニ」と副題がついて再公開されました(初公開時はロシア語版)。
「ピロスマニ」は、所属していたサークルでのオールナイトイベント上映の一本として自主上映しましたが、今にして思えば凄いセレクトです(笑)。ただ、見たかどうかさえ記憶が曖昧…。あるいは見たのに寝てしまったのかも(笑)。
こちらも近日公開となる「やがて海へと届く」。
中川龍太郎監督の「わたしは光をにぎっている」(2019年)は東京出張の折に新宿武蔵野館で見ましたが、独特の世界観がありました。
「やがて海へと届く」のポスターは、ミステリアスで思わせぶりな雰囲気を醸し出しています。そこからイメージしたのは「櫻の園」。中原俊監督が1990年に発表した秀作で、若手の女優さんたちも生き生きとしてました。ポスターのメインビジュアルは、満開の桜の下で演劇部の女の子たちが戯れるデザインだったように思いますが、場面写真の中には「やがて海へと届く」と似たショットがありました。
出演者の中で、とりわけ出色だったのが中島ひろ子さん。岸井ゆきのちゃんは、そのころの中島ひろ子さんを彷彿とさせるものがあります。本作では主演とクレジットされ、ビリングトップ。おそらく物語上からそうなのでしょうが、当然ながら浜辺美波ちゃんの方が先(上)だと思っていたから、これは意外でした。
「櫻の園」はいずれ取りあげるつもりでいました。
以前紹介した、キティフィルムの多賀英典さんらが立ち上げたアルゴプロジェクトの製作で、この草創期には「12人の優しい日本人」「死んでもいい」、いわきでもロケを行った「遊びの時間は終わらない」など佳作、話題作を次々に発表していました。直営館のシネマアルゴ新宿はビルの地下にあり、当時私が勤務していた劇場と構造が似ており、尚更親近感もありました。
中原俊監督は後年自作のリメイクにも挑みましたが、残念ながらこちらは未見。
いわきの桜も今が盛り。もう少ししたら、船引の<願い桜>だ。 (沼田)