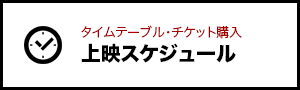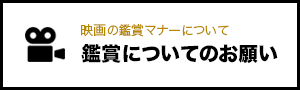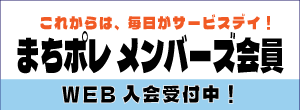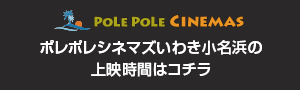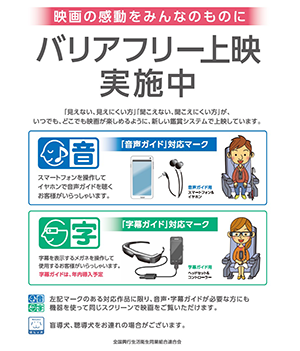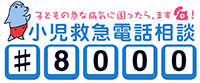◆スポーツ選手などが新記録を打ち立てたり、あるいは区切りの数字に達したりすると、よく「通過点」という言葉を口にしますね。壁新聞もいつの間にか150号を超えたのですが、まさにその心境です。
ただ、今回再掲する3年半前の60号の時は、すごく意識しました。それは見出しにも表れています。前任地で隔月発行していた番組表が、いわきへの異動のため60号を目前にして終了してしまったということも多分にあります。
尚、本文中にあるいわきアリオスへの転載は、この電子版を始めたことにより終了しています。
◆『まちポレ壁新聞』最新154号『映画館のある生活』(4/7発行)は、5階ロビーに掲示中です。
※121号以降のバックナンバーのファイルもあります。
まちポレ壁新聞 №60 2021年11月1日
アニバーサリー
Time My-Scene ~時には昔の話を~ (vol.25)
全く個人的な感覚ですが、「60号」という数字には区切りを感じています。月刊だと丸5年、隔月ならちょうど10年という節目に当たるからです。
本紙の場合は、3年と2ヶ月で達したわけですが、数ヶ月空いた時が2、3度あったかと思えば、一日に2号出来たこともあります(発行日は<掲示日>の目安みたいなもので、一致しません)。
創刊時には、まちポレの番組同様<隔週>を目指したいと書いていましたが、読み手を想定していないし、タイムリー性も意識していないので、思い立った時が発行日というポリシー(笑)ゆえに。
例えば、映画監督が何十年も新作を撮らなくても<元>映画監督とは言わないのと同様、<廃刊>を宣言しない限りはいつでも準備中ということになりますね。
最初は、出して掲示したら終わりでいて、目を通してくれる方もせいぜい片手ぐらいだろうと踏んでいました。恐らくそれは当たっていると思うのですが、その後、バックナンバーをラミネートして<古新聞>として並べたり、自分の友人たちにLINEやメールで送ったりし始めました。今では、いわきアリオスのブログにも『まちポレ紙ヒコーキ新聞』とタイトルだけ変えて、同じものを不定期掲載していただいています。
と言っても、内容が内容だけに読者の数が増えているとも思っていないし、あくまでも<理想>は、まちポレのロビーで目にしていただいて、その場がサロン化することなので、電子版が出てもスタイルを変えるつもりはないし。
このところずっと、空いている時間に過去の<古新聞>を整理していました。
当初は、「出したら終わり」で「残す」ことを意識していなかったので、プリントアウトした原本はあってもパソコンには残ってなかったり、あるいは修正前後のがあったりで、今頃やっとバックアップをし始めた次第です(笑)。
読み返していると直したくなるところもあるけれどそれはせず、日本語としておかしなところのみ修正しました。唯一<加筆>したのは、途中まではなかった「見出し」を追加したことですね。当時の視点で見ることは無理だけど、内容からこんなことが言いたいのだろうと判断して。
そして、この作業を見ていた妻はこう言い放ちました。
「それって、終活?」(笑)。
今、映画館での<滞在時間>って、激減していると思うのです。
昔と違って入れ替え制だからある意味当然なのですが、お目当ての映画を見たらそれで終わりという感じですよね。忙しい中を映画の時間に合わせて来場するのだし、車での移動がほとんどだからこれまた当然とは言えるのですが。
でも、鑑賞後の<余韻>に浸って、その空気を感じる場所でパンフレットは読みたいと思いませんか。
そのパンフレットですが、高いですよねぇ。820円か880円が平均かも。映画の記念に気やすく買えなくなってしまいました。逆にそんなにするのなら、ちょっと足してもう1回、あるいはもう1本見ようかと思っちゃいますよね。
私はやっぱり、チョイ足し派の後者だな。
いつもの長いあとがき
冒頭に書いた<60>という数字。
もしこれを年間鑑賞本数に置き換えると、単純に毎週映画を見ているとしても52本にしかならないのだから、年間で60本を見ているとしたら大変な数ですよね。
私は学生時代、年間で240本超という数をこなしたことがありましたが、それは時間もあったし、名画座の料金は今の珈琲代より安くてしかも3本立てなんてザラだったし、8ミリなどの自主映画まで含んでのことなので。三桁いったのはその前後にも一、二度あったぐらいかな。
それでも当然見られる(その前に「選ぶ」という作業があるか)映画は限られるわけで、映画の教科書とでもいうべき作品でも未見のものがたくさんあります。
具体的に言うと、決して大きな声では言えないのですが、「ウエスト・サイド物語」や「サウンド・オブ・ミュージック」を見ていません。恥ずかしいので、発行時にはこのタイトル部分を、機密文書の証拠品のように黒塗りしたいぐらいです(笑)。
前者は、スピルバーグ監督の手により再映画化され「ウエスト・サイド・ストーリー」というタイトルでこの冬に公開されますね。これがちょうど<60年>振り! 未見とは言っても、「トゥナイト」や「アメリカ」「マリア」といった歌はもちろん知っているし、タイトルデザインを担当したソール・バスという名前もこの作品やヒッチコック監督の「北北西に進路を取れ」で覚えました。
スピルバーグ版のポスターデザインもいいですよね。氏はもう亡くなっているけど、クレジットタイトルだけ取っても楽しみだな。
昨年の「天井桟敷の人々」や「カトリーヌ・スパーク レトロスペクティブ」の特集上映をしてくれたザジ・フィルムズが、また<奇跡的>な番組を用意してくれました。知識としてしか知らなかった<歴史的>と言えるような作品が数本あり、中には2本立てもあるようです。これはちょっと楽しみだワイ。
(沼田)